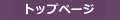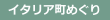トレンティーノ-アルト・アディジェ州の州都であるトレントは、州都といっても人口は10万人程度。背後に山々を望む高原の地方都市というイメージである。もっとも、イタリアの多くの町と同様に、コンパクトな中心部に人が集中しているので、人口の割には賑わっているように感じられる。
 ▲旧市街への入口にあたるシルヴィオ・ドリゴーニ通り。
▲旧市街への入口にあたるシルヴィオ・ドリゴーニ通り。
2007/06
ここを訪れた2007年にはまだ宿のネット予約が一般化していなかったので、シーズンオフの旅行では、町に着いてから行き当たりばったりにホテルを決めることが多かった。だが、このときはたまたま到着の数時間前に電話で予約したのが幸いした。
というのも、乗った列車がトレント駅に着いたとたんに土砂降りの雨。危なく駅で途方に暮れるところだった。もっとも、当然のことながら、私の名前は正確には聞き取られていなかった。
 ▲豪快なポルティコ(アーケード)が続く旧市街、スッフラージョ通り。
▲豪快なポルティコ(アーケード)が続く旧市街、スッフラージョ通り。
2007/06
トレンティーノ-アルト・アディジェ州は、その名の通り、トレントを県都とする南側のトレンティーノ地域(トレント自治県)とボルツァーノ(ドイツ語名:ボーツェン)を県都とする北側のアルト・アディジェ地域(ドイツ語名:南チロル、ポルツァーノ自治県)から成っている。
歴史的にもこの地域はオーストリアとイタリア(ときにはナポレオン)との間で綱引きのように取り合いが展開され、第一次世界大戦後にイタリア王国に組み入れられた。
 ▲ロドルフォ・ベレンツァーニ通りを直進すると、突き当たりにドゥオーモが見えるという劇的な構成。
▲ロドルフォ・ベレンツァーニ通りを直進すると、突き当たりにドゥオーモが見えるという劇的な構成。
2007/06
とはいえ、アルト・アディジェはドイツ語を母語とする人が7割と多数を占め、イタリア語を母語とする人が大勢を占めるトレンティーノとは歴史的にも文化的にも大きな違いがある。それでも同じ州とされたのは、アルト・アディジェを単独の州としてドイツ系が多数を占めることを恐れた戦前のイタリア政府の意向であった。
そんな歴史を頭に入れながらここの町並みや建物を見ていくと、ドイツ文化が色濃いポルツァーノとは違って、ドイツとイタリアの文化が融合しているような気がする。
 ▲歴史的な建造物に囲まれたドゥオーモ広場。ドゥオーモを背にして、右がプレトリオ宮。
▲歴史的な建造物に囲まれたドゥオーモ広場。ドゥオーモを背にして、右がプレトリオ宮。
2007/06
大雨のおかげで翌日の朝は涼しかったものの、昼間はかんかん照り。そのなかを、まずこの町の最大の見ものであるブオン・コンシリオ(ブオン・コンシーリョ)城に向かった。あえて日本語に訳すと「良き教えの城」といったところだろうか。
城の一部が催し物の準備のために閉鎖されていたが、その代わりに、残った区画の入場は無料になっていた。ラッキーだったのは、その残った区画こそが城の古い部分であり、トッレ・ディ・アークイラ(鷲の塔)が含まれていたことである。
 ▲外観は地味めだが、内部は手入れが行き届いて収蔵品も見事なブオン・コンシリオ城。
▲外観は地味めだが、内部は手入れが行き届いて収蔵品も見事なブオン・コンシリオ城。
2007/06
印象的だったのは、塔の内部に描かれたフレスコ画「Ciclo dei Mesi」(月々の巡り)である。1400年ごろに描かれたとのことで、市井の人びとの毎月の生活を月ごとに塔の内側に描いたもので、ブリューゲルを思わせる素朴な農民画に心惹かれた。
 ▲ブオン・コンシリオ城から眺めたトレントの町並み。前日の大雨のおかげで空気が澄んでいた。
▲ブオン・コンシリオ城から眺めたトレントの町並み。前日の大雨のおかげで空気が澄んでいた。
2007/06
短い滞在だったが、澄みきった空気と晴れた空のおかげで、トレントの印象はすこぶるよい。居心地もよさそうである。もう少しスケジュールに余裕があったなら、ゆっくり滞在してみたかった。ぜひ再訪したい。
車窓から遠ざかっていく町並みを見ながら、私の脳裏に一つのフレーズが浮かんだのだった。──帰れトレントへ