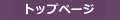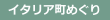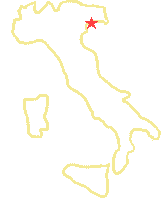
対岸のメストレ駅を発車した列車は、海上に延びた橋をゆっくりと渡りはじめる。そして、海の向こうに見えていた茶色の固まりがだんだん大きくなり、ひとつひとつの建物が見分けられるようになると、やがて終着駅ヴェネツィア・サンタルチア駅である。車窓に映るこの約10分間の光景は、ヴェネツィアという非日常的な空間に入るための最高の演出といっていい。
1981年、初めてこの駅に降り立ったのだが、そのときの感動は忘れられない。駅を出ると、もうすぐ目の前が運河。ゴンドラやモーターボートがひっきりなしに行き交い、船の起こした波が、年輪を重ねたであろう建物を洗っている。
 ▲大陸側のメストレとヴェネツィア本島を結ぶリベルタ橋の上を列車が走る。
▲大陸側のメストレとヴェネツィア本島を結ぶリベルタ橋の上を列車が走る。
1990/08
 ▲大運河にかかるアッカデミーア橋。サンマルコ広場はもうすぐ。背後の側にリアルト橋がある。
▲大運河にかかるアッカデミーア橋。サンマルコ広場はもうすぐ。背後の側にリアルト橋がある。
1985/10
そして、町の中に一歩踏み出すと、路地と運河が迷路のように入り組み、どこを見ても自動車の姿はない。まさに、非日常的な不思議な空間なのだが、もっと驚くのは、そんな不思議な町で何万もの人が日常生活を送っていることだ。これを奇跡と言わずにになんと言えばよいか。
▼水上バス(バポレット)は観光客も乗るし、地元の人も乗る。 2000/09

 ▲鐘楼からサンジョルジョ・マッジョーレ島を望む。手前はサンマルコ広場。 1990/06
▲鐘楼からサンジョルジョ・マッジョーレ島を望む。手前はサンマルコ広場。 1990/06
ヴェネツィアの起源は、6世紀ごろ、アッティラ王率いるフン族やゲルマン諸族に追われた人びとが、本土に近いトルチェッロ島に住みついたことにさかのぼるという。
その後、人びとはラグーナ(潟)の中に杭を打ち、現在のヴェネツィア島の土台をつくったのである。遊牧民であるフン族は、一説によると匈奴の一部が漢に追われて西に流れたものと言われているから、ヴェネツィアはその誕生のときから、東方世界とは縁が深いわけだ。
 ▲大運河にかかるリアルト橋付近をゆくゴンドラ。周辺にはレストランや商店が建ち並んでいる。
▲大運河にかかるリアルト橋付近をゆくゴンドラ。周辺にはレストランや商店が建ち並んでいる。
2011/02
マルコ・ポーロが出航したのもヴェネツィアの港だったっけ。そんな歴史に思いをはせれば、サンマルコ広場に面した大聖堂の装飾やドゥカーレ宮殿のアーチに、イスラム建築の影響が強く感じられるのも不思議ではない。ここはアジアの玄関口なのだ。
1981年9月のヴェネツィア




これまでヴェネツィアには6回訪れたのだが、そのよさを本当に知ることができたのは3回目の訪問あたりからである。それまで、あまりのできすぎた町の姿に、正直な話、まるでどこかの遊園地を訪れたかのような空虚さを感じていたのであった。
 ▲ヴェネツィアの魅力は運河だけではない。路地をうろうろと歩いていたら、木漏れ日の美しい小さな広場に出た。
▲ヴェネツィアの魅力は運河だけではない。路地をうろうろと歩いていたら、木漏れ日の美しい小さな広場に出た。
2000/09
しかし、ヴェネツィアはそんな底の浅い町ではなかった。だてに、ゲーテやバイロンが訪れて感動したわけではなかったのだ。
もちろん、大運河も素晴らしい。サンマルコ広場も美しい。リアルト橋も優雅だ。だが、それだけにとどまらず、知れば知るほどヴェネツィアは奥深い魅力を持った町だということがわかってきたのである。
▼自動車が通らない狭い路地は猫の天国。 2000/09

 ▲すれ違うのがやっとの路地もあちこちに。 1990/06
▲すれ違うのがやっとの路地もあちこちに。 1990/06
3回目の訪問でしみじみ感じ入ったのは、迷宮のような路地と運河である。「3回も来て、やっとそんなことに気づいたのか」と笑われそうだが、事実だからしかたがない。
人がやっとすれ違える路地を歩きながら、いつのまにか方向感覚を失い、何時間でも迷っていられる幸福感をようやく味わえたのである。
まあ、自分はそんなヒマ人ではないという人のために、どの広場にも「サンマルコ」「リアルト(橋)」「駅」の3つの方向が記されているのでご心配なく。
 ▲ゴンドラの競技会があるのか、本島から外海に出たあたりで、ゴンドラを漕ぐ練習をしていた親子がいた。
▲ゴンドラの競技会があるのか、本島から外海に出たあたりで、ゴンドラを漕ぐ練習をしていた親子がいた。
2000/09
 ▲細い運河が網の目のように走り、無数の橋が架かっている風景は、ヴェネツィアだけで見られる風景だ。
▲細い運河が網の目のように走り、無数の橋が架かっている風景は、ヴェネツィアだけで見られる風景だ。
2011/02
さて、4回目の訪問で実感したのは、車が1台も通らない社会の素晴らしさ。
印象的だったのは、豪華ホテルのダニエリから、ミンクのコートを羽織ったご婦人が、数人の男性を従えて歩いて出てきた光景であった。ほかの町ならば、ホテルの玄関に横付けしたリムジンだかハイヤーだかに乗っていたことだろう。少なくとも人の移動において、ヴェネツィアは格差の少ない社会である。たぶん。
付け加えていえば、車が通らないから路地はネコの天国でもある。
そして、恥ずかしながら5回目にしてようやく味わうことのできたのが、町なかに何軒もある「バーカロ」(Bacaro)の楽しさである。
バーカロとは、日本風に言えば「一杯飲み屋」。路地の奥にひっそりと息づく立ち飲みのワインバーだ。地元のワインならば1杯が200円弱。高級ワインでも数百円で飲める。
 ▲ヴェネツィア最古のバーカロといわれる「ド・モーリ」の入口。
▲ヴェネツィア最古のバーカロといわれる「ド・モーリ」の入口。
2000/09
2000年9月、夕食前に、あるバーカロに立ち寄った私と妻は、ワインをしこたま飲み、店の人に勧められるままに「チケッティ」の盛り合わせを食べてしまった。結局、それだけで腹一杯になった私たちは、楽しみにしていたレストランをキャンセル。翌日もまた同じ失敗を繰り返し、3日目にようやくバーカロの主人の誘惑を振り切り、ワインを飲むだけで店を出ることができた。注意されたし。
言い換えれば、それだけ楽しいバーカロ通いなのであった。
▼狭い路地と路地の間にある小さな広場。 2000/09

 ▲昼なお薄暗い運河を船が行く。 1990/06
▲昼なお薄暗い運河を船が行く。 1990/06
仕事帰りのおじさん、近所のおばさんが、マスターと挨拶して一杯引っかけて帰る姿は、見ているだけでもうらやましい。
楊枝にささった「チケッティ」と呼ばれる「おつまみ」は、1つ100~200円くらい。旅行者にとっては、レストランでの夕食前に立ち寄るのもまたいい。だが、食べ過ぎには要注意なのである。