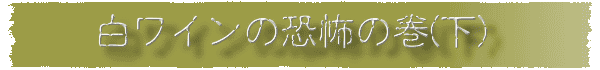 |
|
居酒屋に入ってきたのは、10人ほどのイタリア人の団体であった。年は40代後半から50代前半といったところだろうか。女性も2、3人交じっていた。 何よりも驚いたのは、どの人もこの店に似つかわしくない、きちんとした身なりをしていたことである。しかも、みなインテリっぽい風貌である。それでいて、間違えてこの店に入ったきたわけでないらしい。謎は深まるばかりであった。 彼らは、私のいるテーブルの2つ奥に席をとった。すると、どこからともなく店の主人らしい男の人が現れ、これまたどこからともなく軽食が運ばれてきたのである。 すでに750ccのワインを飲んでいた私は、何事が起こったのか把握できないまま、ぼんやりとその光景を眺めていた。 彼らの歓談の様子は、イタリア人らしくにぎやかで楽しそうではあったが、どことなく抑制がきいていて上品である。 そのうちに、店の主人がアコーディオンを持ち出して、古い歌を次々に弾きはじめた。まるで映画の一場面のようである。ネオレアリスモの居酒屋は、しだいに映画「カサブランカ」の居酒屋になってきた。あまりにも楽しそうな雰囲気に、私も加わりたくなってきた。テーブルの上に並ぶ食事も魅力的である。 | |
| いつのまにかテーブルにはカバーがかけられ、店主らしき男性がアコーディオンをひきはじめた。 撮影 : 1996/07 Frascati |

|
|
と、よほど物欲しそうな顔で見つめていたに違いない。ついにお呼びがかかった。 もともと遠慮というものを知らない駄菓子青年である。手招きされるままに、そそくさと席を立っていった。ローマに帰るには、9時58分のローマ・オスティエンセ行きの最終電車にさえ間に合えば大丈夫だとすでに調べてある。 手招きしてくれた紳士は、ナポリの弁護士だった。なんと、彼の家はナポリのメルジェッリーナ地区の丘の上にあり、私が両親といっしょに1週間前に泊まったホテルのすぐそばだということがわかった。 「私たちはね、1年に1回集まって、そのあとで必ずこの店に来るんですよ。私たちはもう食べてきたので、どうぞ遠慮なく食べて飲んでください」 こう言って、白ワインをなみなみとついでくれる。どんな集まりか聞けばよかったのだが、飲み食いに気をとられて質問するのを忘れてしまったのが返す返すも残念である。 そして、30分だったか、1時間だったのか、それとも2時間もいっしょにいたのかよくわからないが、ただひたすら楽しい時を過ごした……ような気がする。なにしろ、つがれるままに白ワインを飲み続けたために、何を話したのかまったく記憶にないのである。アコーディオンに合わせていっしょに歌ったような気もするが、よく覚えていない。 そして、彼らは帰っていった。私は、まるで店の人間のように、あいさつをしたり握手をしたりして階段まで送っていったのである。 いつのまにかほかの客もいなくなっていて、店には主人らしいアコーディオンのおじさんと私だけになっていた。嵐が去ったあとの居酒屋は、急に静かになってしまった。 「こんなにあまっているから、好きなだけ食べて飲んで行け」 親切な人である。いま思うと、満腹中枢がいかれてしまっていたとしか思えない私は、店主のおことばに従って、さらに白ワインを飲み、生ハムやらサラダやらを胃袋に収めていったのである。 店を出たのは9時半。飲み食いした総量にくらべれば、支払った金はほんのわずかなものだった。私は、いい気分になって、ふらふらと駅への坂を下りていった。 ----いやあ、実に楽しいひとときだった。それにしても、不思議な体験だったなあ。 ナポリの弁護士にもらった名刺をもう一度見た。木の葉に変わっているんじゃないかと思ったが、やはり名刺のままだった。 | |

|
イタリアの南部から中部にかけて、このような丘上都市(山岳都市)が点在している。フラスカーティも、このような町の一つである。 撮影 : 1996/06 Castiglione in Taverina |
|
小さな終着駅から4両編成の電車に乗ったのは、数人の客だけだった。駅員はいないので、切符は車掌から買うことになっているらしい。 電車が動きだしたとたん、胸にこみあげるものがあった。といっても、こみあげてきたのはしみじみとした満足感ではなく、白ワインを1リットル以上も飲んだことによる不快感であった。 ----うっ、こりゃダメだ。 このとき駄菓子青年の頭に、十数年前フィレンツェの安下宿で下水を詰まらせた事件がよぎった。 ----は、早く……、トイレに行かねば……。 だが、その車両にはトイレがなかった。だからといって、ほかの車両まで歩いていく気力もない。電車の窓を開けて新鮮な空気を吸い、必死でガマンした。 そのうちに、途中の駅で客が1人降り、2人降りして、この電車に乗っている客は私だけになったようである。しかも幸いなことに、線路の周囲は一面の草原らしい。 そこで、私は電車の窓から顔を出して、左右を確認しつつ、ゲ□(←これはあくまでも伏せ字の四角であって、けっしてカタカナのロではありません)を吐いた。たんまりと飲み食いをしたかいあって、それはそれはかなりな量であった。ひとしきり吐いてしまうと、もうすっきりした。 周囲は草地のように思ったのだが、もしかするとブドウ畑だったかもしれない。なにしろ、真っ暗なのでわからないのである。もしブドウ畑だったとすると、1996年もののフラスカーティのワインには、私の胃で消化しかかったものを肥料として育ったブドウが含まれているかもしれない。心して飲むようにしていただきたい。 ところで、電車の切符であるが、とうとう車掌はまわってこなかったので、めでたくローマまでただ乗りができたのである。吐き気も収まって、これはまさに二重の喜びであった。 私にとって、これが白ワインにまつわる麗しい思い出なのである。 | |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページ | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |