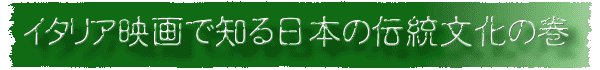 |
|
これは、1985年のミラノでの話。この無駄話をはじめから読んでいるヒマな方には、駄菓子青年がイタリア警察に立て続けにお世話になったときのことだと言えば、すぐにおわかりになることだろう。 夕方、ミラノ中心部のドゥオーモ近くをぶらぶら歩いていると、1枚の映画のポスターが目に止まった。そこには、のっぺりした顔の、ちょっときれいな日本女性が写っていた。どこかで見た顔だと思っているうちに、少し前に日本で耳にしたニュースを思い出したのであった。 それは、「アッシジの聖フランチェスコ」「愛の嵐」などで有名な、イタリアの女流監督リリアーナ・カヴァーニが、三島由紀夫の小説を翻案した映画を撮っているというものだった。 ----ほほう、映画は完成したんだな。そうそう、この女優は高樹澪(たかき・みお)だったっけ。 いまでは知る人も少ないだろうが、なんとなくミステリアスな雰囲気の彼女は、ごく一部にかなりの人気があった女優である。 映画の題名は忘れていたが、この文章を書く前にインターネットで調べたところ、「Interno Berlinese」(インテルノ・ベルリネーゼ--「ベルリンの内側(内幕)」っていう意味かな)であることを思い出した。 さて、その映画の上映時間をと見ると、すぐにも次回がはじまりそうではないか。 ----せっかくだから見ていくか。どうせヒマだし。 私は、旅先でのモットーを再確認し、切符を買って場内に入ったのであった。 |
|
そこは、かなり大きな映画館で、客の入りは三割から四割といったところである。 映画の舞台は第一次世界大戦前後のベルリン。主人公の高樹澪は、大使だか公使だかの娘という設定だ。 いつも和服を着て、無口で無表情な女性である。いかにも、西洋人が考えている伝統的な日本女性の姿である。 そして、彼女のそばには、身のまわりの世話をする乳母らしき女性が、これまた無口のまま、つねに付き添っている。 |

|
|
| ミラノのドゥオーモの屋根に登ると、町が一望できた。 撮影 : 1985/11 Milano
|
||
で、深窓の令嬢である彼女は、いつしかハンサムな(死語)男と恋に落ちる……というのは、お決まりの展開である。しかも、相手は敵国のえらい人の息子だったか反体制派の青年だったか……これは記憶が定かではない。 だが彼女には、自分から行動をする自由もない。そこで、親の目を盗んで、逢い引きを重ねるというわけだ。乳母のような女性がその手引きをするところなんざ、平安時代の物語を読んでいるようで、なかなか興味深かった。 そこまではいいのだが、問題は、彼女が初めて男の部屋に行った日のことである。部屋に二人きりになり、彼女はみずから帯をほどくと、まるで魔法のように着物がするすると下に落ちていく。そして、彼女の肩があらわとなる……。 純情な私は、事の成り行きにドキドキしながらも、食い入るようにスクリーンを見つめていた。 そして、その直後、驚くべき光景が目に入ったのである。 なんと、彼女の背中いっぱいに極彩色の彫り物(入れ墨)が彫ってあるではないか。 ----そ、そ、そんなばかな……! なんで深窓の令嬢が彫り物を……。 思わず私は、この驚きと不満を誰かと分かち合おうと周囲を見まわした。だが、まわりにいるのはイタリア人ばかりである。みんな、真剣にスクリーンを見つめているだけなのであった。 ----うう、断じて腑に落ちないぞ……うーっ、でも、まあ、いいか。親に隠れて彫り物を入れたという設定かもしれないし……。ひとまず、そういうことにしておこう。 何事にも楽観的な私である。好意的に解釈することにして再び画面に顔を向けた。 話が進んでいくにしたがって、主人公は本性を現していく。次々に男をからめとっては、虜にしていくのだ。会ってみたいような会いたくないような怖い女である。 あまりの人物設定のひどさに、日本人に対する印象が悪くなるんではないかと心配になったほどである。 実際、前半が終わって休憩時間にロビーで休んでいると、気のせいか私を見るイタリア人の視線が厳しく感じられた。 ----こんな女を日本の代表だと思うなよ! と言いたかったが、口に出すわけにもいかず、ぼんやりしているしかない。当時は、女がそれほどまでに恐ろしい生物だとは思っていなかった純情な駄菓子青年であった。 さて、後半の筋は忘れてしまったが、戦争が激しくなって彼女の一家は日本に帰るのだったか、とにかく彼女は男と別れなくてはならなくなったのである。 そして、最後の逢い引き。なぜか場所は日本風の茶室である。 たたみに座り、目と目を合わせる彼女と彼。そして、いきなり二人は抱き合ってたたみの部屋を転がりまわる。 その直後である。またもや信じられない光景が目の前に繰り広げられたのである。 |
|

|
ミラノの中心部近くに、壁全体にアルマーニの広告が描かれているビルがある。 撮影 : 1985/11 Milano |
|
茶室のなかでもつれあった二人は、なんといきなりジャボンという音を立てて水のなかに落ちてしまったのである。どうやら、茶室のどまんなかに、一畳分だけ穴が掘ってあり、まるで風呂のように水がはってあったらしい。 ----ば、ばかな……いや、それともこれは……そうかそうか、これは笑うべき画面なんだ。 一瞬のうちに私の頭によぎったことを、順に整理したらこうなったかもしれない。 私は、思わず声を出して笑いそうになった。最後の逢い引きの日に、この日本女性が、茶室に大仰な“いらずら”を仕掛けたというオチだと判断したからである。 だが幸いなことに、大口を開けたところで、自分がイタリアにいることを思い出した。 もしかしたら……と思い、周囲を見まわすと、やはりイタリア人たちは真剣な顔でスクリーンを見つめていたのである。 口を大きく開いたまま、声を出すこともできず、私はひととき欲求不満を味わうほかなかった。 --こりゃ、とんでもない映画だ~。 映画が終わると、私はそそくさと映画館をあとにした。 映画が完成したのに、なぜ日本で上映されないのか、そのわけがわかった。いくらなんでも、これを日本人の前で公開するわけにはいかないだろう。 のちに、どこかの雑誌で、撮影のときの裏話を読んだことがある。 それによると、さすがに日本人の俳優が、「ふつうの女性は入れ墨なんかしませんよ」と監督に進言したそうだ。だが、かの大監督は「いいじゃないの、おもしろいんだから」とおっしゃったそうな。 それにしても、本当の茶室には、あの映画で見たような風呂のようなものがあるのだろうか、もしかして私が無知なだけなのかも----そう思って不安になったのも事実である。いまでも、テレビや雑誌で茶室が出てくるたびに、無意識のうちに、どこかに水を貯めている場所がないか探してしまう私なのであった。 余談だが、昔、ツムラのコマーシャルで、たたみの部屋のなかに1畳分だけ風呂を切って、そこに山崎努がつかっているというものがあった。もしかすると、あれを見て映画のセットをつくったのかとも思うきょうこのごろである。 |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページ | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |