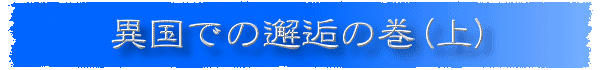 |
1981年12月。フィレンツェに冬がやってきて、秋の学期も終わりを迎えた。 手持ちの金は残り少なくなっていた。残りの金を使ってヨーロッパ旅行をして帰るか、それともどこかで金をかせぐ算段をしてここに居残るか、決断をしなければならない。 金をかせぐといっても、そんなつてはなかったし、無理して探すのも面倒くさく思えた。それよりも、手元にある未使用のユーレイルパスを使えば、とりあえず1か月ほどは旅費なしで1等車が乗り放題だ。 そろそろ、1か所にいるのは飽きてきたところである。また、あちこちをまわってみたくなった。 ----日本に帰ったら、イタリアで勉強した知識を使って、大学院でも入ろうかな。 別に、特定の大学院にあてがあったわけではない。いまから思えば実にいいかげんで無謀な決断であった。もし、あのとき無理をしてでもイタリアに残っていたら、私の人生は大きく変わっていたであろう。 もしかすると、イタリアの富豪の娘に見初められて、贅沢な暮らしをしていたかもしれない。あるいは、当時ヨーロッパで活動中だったらしい東アジア某国のスパイに誘われるまま、どこかに拉致されていたのかもしれない。よいほうに変わっていたのか、悪い方に変わっていたのか、それは誰にもわからない。 | |

|
冬になると、どんよりとくもった日が多くなる。フィレンツェの町もどこか、もの寂しさが漂って好ましい。 撮影 : 1981/11 Firenze |
|
「ダガシくん、難民学校に張り紙をしてきたわ。ルームメイト募集のな」 S氏は言った。手まわしのいいことである。私はといえば、自分がこの部屋からいなくなったあとのことなど想像すらしていなかったので、ちょっと不思議な気分であった。生きているうちに、葬式の相談を受けたら、こんな気持ちになるのだろうか。 「ええっ、あそこで募集をしたんですか? いったいどんなやつが来るんだか……」 どちらかというと神経質なS氏である。難民学校に来るようなアラブ人やアフリカ人と、はたしてうまく同居できるのか心配ではあったが、もとより私にはかかわりのないことである。 さて、均一料金のユーレイルパスを使うなら、鉄道運賃の高い北ヨーロッパに行くのがお得ではある。だが、ときは真冬になろうというころ、考えただけでも寒い。考えたすえに、スペインとポルトガル方面に出かけることにした。ことばもイタリア語に近いので、少しは通じるのではないかと思ったからだ。荷物は、安下宿に預かってもらうことに勝手に決めた。 |
||
|
「おばさん、2週間か1か月くらいで帰ってくるから、荷物を預かっておいてもらえる?」 「ああ、いいわよ。じゃ、この物置に入れておくからね」 おばさんは、二つ返事でオーケーしてくれた。 これで旅の準備は万全である。荷物は、当時、イタリアで出まわりはじめたマンダリーナダック製の大きめのショルダーバッグ1つ。中身は貴重品を別にすれば、一眼レフカメラ1台に着替えが少々。旅は荷物が少ないに限る。新しい旅に向けて気分が盛り上がる駄菓子青年であった。 |

| |
| サンマルコ修道院は、観光客も比較的少なく、静かな場所であった。中庭のアーチは、どう見てもイスラム建築の影響である。 撮影 : 1990/09 Firenze |
||
|
さて、いよいよフィレンツェを離れる前日の夕方。私は最後の散歩に出た。 その日は、やけに夕日がまぶしかったことを覚えている。くもり空の多い冬にしては、晴れ上がった日だったからかもしれない。町が、夕陽に赤く染まっているようにさえ感じられるほどだった。 「ああ、この町ともきょうでお別れかあ。短かったけど、いろいろなことがあったなあ」 当時は、冬になるともうあまり観光客はいなかった。なかでも、観光客のあまり訪れないドゥオーモの東側をぶらぶら歩いていった。このあたりは、ごく普通の店が立ち並んでいる地域で、なんとなく気に入っていたところであった。そして、郵便局のあたりをサンタ・クローチェ教会に向かっていたときである。私の耳に、日本語らしいことばが入ってきた。 「○○さん、○○さん」 女性が私の名を呼ぶ声のように聞こえた。しかも、名字である。 だが、この町で私を名字で呼ぶ女性はいない。語学学校の同級生をはじめ、女性の知り合いは、みな私をファーストネームで呼んでいる。 ----ああ、日本語で空耳が聞こえるようじゃあ、いけないなあ。 ホームシックなどというものには、一度もかかった覚えがないのが自慢の私だったから、このときはちょっぴりショックであった。 ちょっと感傷的になりながらも、そのまま歩いていくと、また声がした。 「○○さん、○○さん」 こんどは、前よりもはっきりしている。 ----ああ、いよいよ、おしまいだなあ。やっぱり日本に帰らなくちゃいけないってことかなあ。 「○○さんったら!」 こんどは、耳のそばで声がした。驚いて振り向くと、見覚えのある女性が立っていた。 (つづく) |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページ | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |