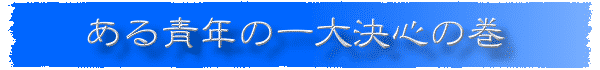 |
冬も本格的になると、夜の散歩もおっくうになってくる。そんなときには、安下宿で安ワインでも飲みながら、とりとめもないおしゃべりをするのが一番である。 S氏と私がいる安下宿は、町の真ん中にあるためか、週に2、3回は、日本人やら中国人やらが集まってくるようになった。 そんなある日のことである。 その日は、私とS氏のほかに、千葉県出身のイッセイ君がいた。例によって、イタリア人はいいかげんだの、いや意外に几帳面なところがあるだのといった話をしていた。 イッセイ君は、私よりも3、4歳ほど年下だったと思う。 「本名はかずおと読むんだけれど、イッセイと呼んでください」 三宅一生を意識したのだろうか。変なやつだというのが第一印象であったが、付き合ってみると、良識と気概のあるやつであることを知った。 美術の勉強をしにイタリアに来たというのだが、とくに学校に通っているわけでもなかった。かといって遊びほうけていたわけでもないようである。例の「難民学校」にも、ときどき顔をだしてはいた。 |
|
私よりも数か月ほど前からフィレンツェにいたためか、イタリア人の友人も多かった。しかも、遊び好きの兄ちゃんたちと仲がよかったらしい。そのため、難民学校の語学教室でも、私が聞いたことのないようなことばを口にする。 だが、そんなことばを聞くたびに、インテリの先生はしかめつらをするのが常であった。 「それは、道の上のことばだ」 かなり俗っぽいことばだったらしい。 とはいえ、そんなことばを知っているイッセイ君を、ちょっとうらやましくも思った駄菓子青年である。 |

| |
| ドゥオーモの東側の地区には、地元の人がふつうに生活する町がある。 撮影 : 1985/11 Firenze |
||
|
「ところで、ぼくの日本人の友だちの話なんですけどね」 赤ワインがほどよく体を暖めてきたころ、イッセイ君が切り出した。 もっとも、私は、ただ安い赤ワインを飲むことに心を集中していたので、いつ話題が変わったのかもわかっていなかった。いい気持ちになって、ただぼんやりと二人の会話が耳に入るのに任せていたというのが正直なところである。 「フィレンツェにいるやつなんですけど、パドヴァに住んでいる年上の女性と付き合っているんですよ」 パドヴァというのはイタリア北東部にある大きな町で、ヴェネツィアから列車で30分ほどのところにある。 イッセイ君がこういうと、S氏は合いの手を入れた。 「ほほう。イタリア人の女性かいな」 「ええ。それで、こんど本人たちはいっしょに住もうということになったんだとか。彼は結婚してもいいかなんていっていましてね」 「ふふん、それで」 「ただ、問題があって……。彼女に旦那がいるんですよ。でも、ずっと別居していて離婚同然なんだとか。ただ、ほら、イタリアってカトリックだから、離婚は大変でしょ」 いまはどうなったか知らないが、当時はちょっとやそっとでは離婚できなかったと聞いていてる。 「チンクエ・アンニ・ディ・セパラツィオーネもまだだというし……」 イッセイ君の口から聞き慣れないことばが出てきて、私は興味を示した。 「なに? その5年間のなんとかって」 「5年間の別居ですよ。昔は離婚はまったくできなかったらしいけど、いまじゃ5年間別居していれば、裁判所で離婚が認められるっていうことで……。彼女の場合は、もう4年近く別居しているというから、あと1年ほどで正式に離婚できるといっていましたよ」 「へえー、そんなことがあるのかあ」 イッセイ君は世の中のことをよく知っていた。 彼は続けた。 「それで、どうすればいいかって相談を受けているんですよ」 「ふうん」 私はため息をついた。自分が、町を散歩したり、バスや電車に乗ったりして喜んでいる間に、同じフィレンツェでそんな人生を送っている日本人がいるのである。なんだか自分がいやに幼く思えてきたのである。 --ああ、人生だなあ。まるで小説の中の世界みたいじゃないか。そんなのも悪くはないなあ。 とはいえ、話の主人公は自分の知らない人である。いまひとつ、ピンとこなかった。 S氏はと見れば、細い目をさらに細めて、腕を組みながらじっとイッセイ君を見つめている。何かおもしろいアドバイスでもあるのかと、私はちょっぴり期待して待っていた。 |
|

|
パドヴァの町の中心部。イッセイ君はこの町のどこかにいるのだろうか。 撮影 : 1985/11 Padova |
|
「その友だちってさあ……」 数秒の沈黙ののち、S氏は口を開いた。 「イッセイ君、キミのことじゃないの?」 私は驚いた。どうしてそんなことを言うのか、理解ができなかった。 そこでイッセイ君はと見ると、くりくりした目でS氏を見つめている。二人は黙って見つめ合っていた。 2、3秒ほどたったところで、気のせいかイッセイ君のほほがゆるんだように見えた。 「実は……そうなんですよ」 「ふふふ、そうやろな」 S氏は勝ち誇ったように微笑んだ。 事態は意外な展開を見せた。 「イッセイ君、どうするんや」 「行きますよ」 「そうやろな。行くしかないやろ」 どうも、このときの私は、二人の会話をぼんやり聞いていただけで、一人仲間はずれのような気分であった。あえていえば、夢の中で他人の会話を聞いていたような印象である。 --ふうん、そんなこともあるんだなあ。そんな出来事って、遠い世界の話かと思っていた。 でも、この話の主人公は目の前にいるイッセイ君である。そう思うと、3歳だか4歳だか年下の彼が、ずいぶん大人に見えたのであった。 そしてS氏である。よくもまあ、話の主人公がイッセイ君だと見抜いたものだと思った。そのことだけで、1歳しか年の違わないS氏が、これまたずっと大人に見えたのであった。 イッセイ君の決心は固かった。S氏に相談してもしなくても、結論は決まっていたのだろう。すでに、翌週には出発することに決めていたらしい。 「じゃあ、がんばれよ」 「パドヴァに行ったら連絡くれよ」 「お二人ともお元気で」 最後に握手をして別れた。イッセイ君の顔を見たのは、その約2週間後、たまたまフィレンツェ駅構内で会ったのが最後である。 あれから20年以上もたってしまった。イッセイ君も、いまでは40歳を越えたいいおっさんになっていることだろう。まだパドヴァにいるのだろうか。それとも、また別の土地でたくましく生きているのだろうか。 そういえば、最後にイッセイ君に頼まれたことがあった。美術の勉強にきた彼は、イタリア人があまりにも東洋美術や日本美術を知らないことを嘆いていた。 「ダガシさん、日本に帰ったら雪舟の画集を買って送ってくださいよ。イタリア人に見せてやるんです。お願いしますね。これがパドヴァの住所ですから」 イタリア人に日本の文化を伝えたいという気持ちは、私も同じである。「おう、帰ったらすぐに送るよ」とかなんとか、調子のいい返事をした。 その約束を忘れたわけではなかった。でも、日本に帰ってきた直後は、もう毎日が放心状態で何もする気が起きなかった。おまけに、金を使い果たしてきたので、画集など買うことができない。 もう少し、もう少し、と思ううちに、1年たち、2年たってしまった。そして、いまだに雪舟の画集は送っていないのである。パドヴァの住所もどこかに行ってしまった。 イッセイ君は怒っているかなあ。そんな雪舟な、なんて言いながら。 |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページ | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |