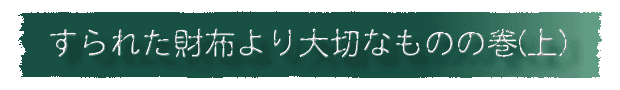 |
|
これもまた1985年、ジェノバ警察に連行されて署長の「歓迎」を受けてから、わずか3日後のことである。 純情で無垢で健全なだけがとりえの駄菓子青年は、あろうことかミラノでもパトカーに乗せられるハメになった。とはいっても、今回は容疑者ではなくて被害者である。 ああ、思い出すだに恥ずかしい。ジャケットを汚されて、脱いだときにポケットをまさぐられたという、よくあるスリに引っかかったのであった。 ジャケットのポケットに財布を入れることなんぞ、この前後の数時間しかやっていなかったのである。だいたい、帰国間際だったので、古いスニーカーを捨てて新しく買った革靴にはきかえ、買ったばかりのジャケットを着込み、ショルダーバッグまで新しいものに替えていたときであった。そうでもなけれは、旅行中にジャケットを着ているなんてことはなかったのである。 ああそれなのに、それなのに……。もうイタリアは慣れちまったぜ、なんて思っていたのが間違いのもとであった。 まあ、真っ昼間とはいえ、薄暗がりで、新しく買ったマンダリーナダックのショルダーバッグに、古いかばんの中身を入れ換えていた私もおろかであった。何か後ろめたい気分でいたことがいけなかった。しかも、相手は20代後半くらいのちょっときれいなねえちゃん……。 財布には、2、3万円の現金とカードが入っていたが、まあトラベラーズチェックが別に保管してあったのが不幸中の幸いだった。 | |

|
どうも、ミラノという町は相性が悪い。来るたびに、なにかしらトラブルに見舞われるのである。 撮影 : 1996/07 Milano |
|
どうも変だと気がついたときには遅かった。あとを追っかけて、近くのバールやら地下鉄の改札やらを駆け回ったが、すでにスリのねえちゃんの姿は見えなかった。 「クソーッ、こんどは胸ポケットに剣山を入れといてやる!」 憤慨しながら歩いていると、近くに何やら怪しげな10人ほどの集団。 「もしや、このなかに……」と、前後の見さかいを失っていた私は、いきなりその輪の中に飛び込んだ。 相手もびっくりしただろう。ぼうぜんとした顔の東洋人が、いきなり駆け込んできたのである。 私は、周囲をざっと見まわしたが、こんな近くに立ち止まって待っているようなマヌケな犯人がいるわけはない。それに、その集団は、みな10代後半くらいの若者ばかりのようであった。 「どうしたんですか?」 こう聞かれて、ふと我に返った。 「財布を盗まれたぁ~」 「え、それは大変だ。おにいさん、いま警察を呼んでくるね」 そのなかの1人が、どこかへ走っていった。 疑った私が愚かだった。スリどころか、平均以上に親切なお坊っちゃんとお嬢ちゃんたちだったのである。 警官を待つあいだ、私はみんなの質問ぜめにあった。 「ねえ、どこから来たの? 日本? じゃ、英語をしゃべれるね」 がっしりした体格の男の子にそう聞かれ、私は胸をはってウソをついた。 「イエ~ス」 「わー、じゃ、ぼくたちも教えてもらおう!」 「私にも教えて!」 かわいい声でそう叫んだ女の子を見て、私は一瞬息が止まった。 ふわふわした白い服と白い帽子に身を包んだ彼女は、年は10代なかばだろうか、知性を感じさせる整った顔だちに、屈託のない笑みが浮かんでいた。イタリアをあちこち旅行したが、こんなにかわいい子ははじめて見た。 そして、私はためらいなく、彼女に「清楚な美」ということばを捧げた。心の中で、ね。 彼女には、確かに後光が射していたのだ。私は、財布をスラれたことも忘れ、しばしうっとりと彼女に見とれていたのである。あとは、何を話したのか覚えていない。 ぼんやりと夢を見ているような気分になっていると、警官がやってきた。 (つづく) | |

|
おまけ:修復中のレオナルド・ダ・ヴィンチ作「最後の晩餐」。当時は、こわい顔をした係員もいなくて、間近で見られたのだ。 撮影 : 1985/12 Milano |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページ | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |