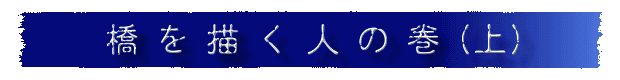 |
|
まだ20代前半だった私にとって、フィレンツェの町はおもちゃ箱のようなものだった。毎日、学校が終わると、狭い旧市街をたっぷりと時間をかけて散歩するのを日課としていたのだが、いくら見ても飽きることがなかった。 そんな晩秋のある日、いつものように夕方の散歩に出かけたときのことである。 ドゥオーモ(サンタ・マリア・デル・フィオーレ教会)の広場を横切り、立ち並ぶ店のショーウィンドーを眺めているうちに、ほどなくアルノ川のほとりにたどりついた。ポンテ・ヴェッキオの上に並ぶ店は、夕日に赤く色づいたように見え、橋の上は地元の人と観光客が入り交じってちょっとした賑わいを見せていた。 さてどうしようかと足を止め、ふとあたりを見回すと、橋に向かってイーゼルを立てている人の後ろ姿が見えた。 ----ほほう、さすがは芸術の都だ。それにしても、こんなところで絵を描くなんて、しゃれているもんだなあ。 私は、どんな絵なのか覗き込もうと、そっと近寄っていった。 ところが、その人の横顔を見たとたん、心臓がどきっと鳴った。 まぎれもなく日本人だった。年のころは50をちょっとすぎといったところだろうか、亡くなった俳優の宇野重吉に似たやせ型の男性である。 その男性は、なにかはりつめたふんいきを周囲に発散していた。私は、それ以上近づいてはいけないような気がしてきて、そっとその場を離れたのであった。 | |
| ポンテ・ヴェッキオの夜景。その「おじさん」は、この橋の姿を毎日毎日描いていたのである。 撮影 : 1996/06 Firenze |

|
|
「ああ、あの人は有名らしいんですわ」 のちに私の安下宿に転がりこむことになった、語学学校の同級生S氏は、私の報告にこう答えた。 「もう何年もポンテ・ヴェッキオばかり描いているらしくて、ビザが切れて強制送還されても、またいつのまにか舞い戻ってくるんだそうですよ。で、とうとうイタリア政府もさじを投げて黙認してるんだとか」 どこからそんな情報を仕入れてくるのか、S氏はまるで見てきたかのようにこう言った。そして、最後にひと言付け加えた。 「日本人の団体旅行者が近くに寄って覗き込んだり、話しかけたりすると、黙って道具を畳んで帰ってしまうらしいんですわ」 S氏の話は、いまとなっては事実かどうかわからない。でも、純情だった駄菓子青年はその話を信じた。なんとロマンチックな話ではないか。 その日から、あのおじさんは、私にとってまるで伝説の人のようになってしまった。だから、その後何度も橋のたもとでそのおじさんを見かけたが、声をかけることはおろか、半径10メートル以内に近寄ることはできなかったのである。 | |

|
サン・マルコ修道院の壁に描かれた、フラ・アンジェリコの名画『受胎告知』。 まわりに人がだれもいないときに見るこの絵は、実に神々しい。 撮影 : 1981/11 Firenze |
|
はじめておじさんを目にしてから、2か月ほどたったある日のことである。S氏と2人でフィレンツェの町なかを散歩していると、向こうからそのおじさんがゆっくりと歩いてくるのが見えた。私はなぜか知らず全身に力が入った。 ----うっ、どうしよう。 しかし、いまさら逃げるわけにもいかず、そのまま歩くしかなかった。そもそも、逃げなければいけない理由もなかったのである。 そして、両者の距離が10メートルほどになったとき、おたがいの目があった。私はどうしてよいかわからず、ひきつったような状態になっていた。 そのときである。おじさんはにっこり微笑んで会釈をしてくれるではないか。それにつられて、私たちも会釈を返した。そして、無言のまますれちがったのである。 こうして、フィレンツェ滞在中ただ一度の接近劇は終わった。 緊張していたのは、私だけではなかったようだ。S氏は、満面に笑みをたたえてこう言ったのである。 「あいさつしてくれたよぉ。ボクたちもここの住人として認められたということですかねぇ」 なに卑屈になってるんだよ、と言おうと思ったがやめた。私も似たようなことを思っていたからである。 やがて冬が来て、おじさんの姿を見かける回数も少なくなっていった。年が変わって私は日本に帰ってきたが、フィレンツェのことを思い出すたびに、あの人はきょうも橋のほとりで絵を描いているのかなあと、ちょっぴり気取って空を見上げるのであった。 その後1985年、1990年とフィレンツェに立ち寄り、ポンテ・ヴェッキオのほとりを歩く機会が何度もあった。歩くたびにあのおじさんのことが頭に浮かんだが、残念ながら姿を目にすることはできなかった。 もっとも、会ってどうしようというわけでもなかったが、それでも気になる人ではあったのだ。 (つづく) | |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページ | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |