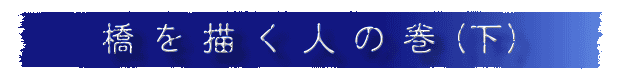 |
|
1996年、今度は両親を連れて初夏のフィレンツェを訪れた。 フィレンツェ滞在は3泊の予定だったのだが、いつのまにか5泊に延びてしまい、ウッフィツィ美術館に入場したのは、まさにその最後の日の午前中のことであった。 「さあ、ひととおり絵も見たし、座ってコーヒーでも飲むかぁ」 そんなことを言い合いながら、美術館の出口を出たときである。 見覚えのある日本人が、こちらを向いて立っていた。 「おじさん!」 思わず、私は叫んでしまった。髪の白い部分が増えて、以前よりもやせていたが、間違いなく、十数年前にポンテ・ヴェッキオで見かけたあの人である。 相手は、突然見知らぬ日本人に呼びかけられて、驚いた様子であった。 |
|

|
小雨にけむる冬のアルノ川。 右側の橋の向こう側に、ポンテ・ヴェッキオがかすかに見える。 撮影 : 1981/11 Firenze |
|
「あの、ボク、十数年前にフィレンツェに勉強に来ていて、いつもポンテ・ヴェッキオのところでお見かけしたんですよ」 こう言うと、おじさんはにこやかな顔になった。 「ああ、そうですか。失礼ですが、覚えていないんですけど……」 はじめて聞いたその声は、おだやかなものだった。 「いや、直接お話ししたこともなかったし……、道ですれちがってあいさつした程度なんです。それにしても、お元気そうで」 おじさんのまわりには、B5サイズくらいの小さな紙に、サインペンのようなもので描いたカラフルなポンテ・ヴェッキオの絵が何枚か並べられていた。色はちがっていたが、どれも同じ角度から描かれていた。 おじさんは意外にも饒舌であった。大病をして、長い間イタリアの病院に入院していたことも教えてくれた。まだ退院したばかりで、しばらく絵は描いていないらしい。 ポンテ・ヴェッキオばかり描いていた理由も、こちらが聞かないうちに教えてくれた。 「私のおかあさんがね、ひとつのことをやりぬきなさいと教えてくれたんですよ。それで、ここに来て、ポンテ・ヴェッキオの素晴らしい姿を見てからは、もうこの橋だけを描いてきたんです」 私は、もう一度おじさんの顔を見た。この人は、ただひたすら同じ橋を何年も描きつづけ、いつのまにか年老いてしまったのだ。一瞬やりきれない気持ちになったが、じっと顔を見ているうちに、なぜかそんな気持ちも消え失せた。そこには、後悔の表情などみじんもなかったからだ。かといって、何かをやり遂げたという晴々とした表情があったというわけでもない。 やりたいことをやっているうちに、いつのまにか年をとってしまったという感じだろうか。うらやましいような、うらやましくないような、複雑な気持ちになった駄菓子青年であった。 「もう年だからねぇ、描いた絵を全部売って、そろそろ日本に帰ろうと思うんですよ」 実家は、九州の南のほうの山のなかだという。いまから日本に帰って日本の社会になじめるのだろうか。それ以前に、家族や親戚は……。私は心配でたまらなかったが、そんなことを口に出す筋合いではない。 「もし、よかったら、この絵を買っていってください。……万リラでいいです」 値段は忘れたが、けっこうな額であった。買いたいのはやまやまだったが、旅行中の私たちにはかなり苦しい。「残念ですが……」と断るしかなかった。 「それじゃ……」 私たちは握手をして別れた。 私は、なつかしさとやるせなさを抱いたまま、無言で両親とともに百メートルほど歩いた。迷っていた。 |
|
ウッフィツィ美術館の廊下からドゥオーモが正面に見えた。 手前のシルエットは展示してある彫刻。 撮影 : 1981/11 Firenze |

|
|
「やっぱり買ってくる」 そう言って、両親をそこに置いたまま、私はウッフィツィの出口に急ぎ足でもどった。 「もどってきたよ」 「おお、買ってくれるのかい」 おじさんはうれしそうだった。私は、3枚あったポンテ・ヴェッキオの絵のうちいちばん明るい色調のものを選んで、お金を渡した。よく考えれば、ブランド物のバッグなどよりずっと安いのである。 するとおじさんは、そばにあった紙袋の中から写真やら雑誌のコピーやらを取り出してきて、はじから私にくれた。 「これも、あげますよ。これも、これも……。もう日本に帰るからね」 写真には、おじさんの若き日の姿が映っていた。レオナルド・ダ・ヴィンチの有名な肖像画の顔の部分を、おじさんの顔にさしかえたコラージュである。雑誌のコピーは、おじさんのことを取り上げた日本の美術雑誌の記事であった。 こんなものを袋いっぱいにもらったあとで、最後におじさんの写真を撮った。そして、「なんだ、なんだ」と寄ってきた野次馬日本人観光客の方に、私たち二人が肩を組んでいる写真を撮ってもらった。 「じゃ、お元気で」 ポンテ・ヴェッキオの絵の入った袋を左手に抱えて、再び私はおじさんとがっちり握手をした。 あれから2年半、おじさんはいまごろ九州でのんびり暮らしているのだろうか。それとも、フィレンツェに舞い戻っているのだろうか。 実は、あのとき買った絵は、まだ紙袋にはいったままなのだ。そろそろしゃれた額でも買ってきて飾ろうと思っている。 | |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページ | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |