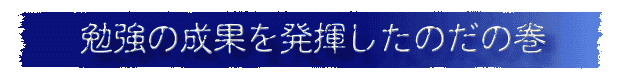 |
|
私が住むことになったフィレンツェの安下宿には、家主であるおばさんの姪も住んでいた。これが、また、おばさんとは似ても似つかぬ超美人なのである。 めったに顔を合わせることはなかったのだが、健康的な美しさに満ちあふれていて、気立てもよい(……と思う)人だった。ひと昔前のイタリア映画の女優を思わせる美貌は、安下宿にはもったいないとさえ思われた。 まあ、そうこうしているうちに語学学校もはじまり、私は充実した留学生活を送ることになる。語学学校の授業がどんなものだったかは、そのうちに書くことになるだろうが、とにかく楽しい日々であった。 で、私の滞在3週間めあたりだっただろうか、私が借りた二人部屋に、語学学校で同じクラスのS氏が転がり込むことになる。 「いやあ、前のところは部屋も大家さんもよかったんやけどね、ドゥオーモの真ん前なんで、朝っぱらから鐘の音がうるさいんですわ」 神戸出身のS氏はこのように語った。フィレンツェのドゥオーモといえば、中心部にあるサンタ・マリア・デル・フィオーレ教会、日本語でいえば、「花の聖母教会」のことである。 こうして、男二人のむさ苦しい生活がはじまったのだが、私より一つ年上の彼も、おばさんの姪の美しさにはぞっこんであった。 「いいなあ、あの人。日本に連れて帰れないかなぁ」 本人をさしおいて、二人で勝手なことを言っあっていた日々であった。 | |
| ドゥオーモ横にあるジョットの鐘楼。S氏は、この正面(写真でいうと左側)に住んでいた。鐘の音がうるさいはずである。 撮影 : 1985/09 Firenze |

|
|
ところで、学校では中級クラスを選択した。日本でイタリア語を少しやっていたからなのだが、これが大間違いであった。FUNGHIが何であるかも知らなかった私にとって(「フンギ殺人事件の巻」をご覧ください)、これは身のほど知らずの選択であった。 クラス分けテストの結果、当然のことながら、中級クラスのなかでも最低レベル(としか思えない)の教室に割り当てられることになる。 とはいえ、結果としてはこれでよかった。分不相応なクラスに行くよりははるかにいいし、なにしろ先生は若い女性であった。私とほとんど年が変わらなかったかもしれない。そして、授業中に「ボラ~レ」などとみんなでカンツォーネを練習する気楽さは、私にぴったりであったといえよう。 ただ、会話だけはちゃんとやりたいと思った。となると、どういうことを聞かれても反射的に反応できなくてはいけない。そこで私は、学校で学んだことをもとにして、日夜繰り返し練習に励んだのである。 はじめのうちは、"Come Vai?"(コーメ・ヴァイ--元気?)と聞かれたら、一瞬間をおいて "Bene, grazie"(ベーネ・グラッツィエ--元気だよ、ありがと)などと教科書どおりに答えていたものが、そのうちに、渋い顔をして "Cosi' cosi'"(コズィ・コズィ--まあまあだね)なんぞと、偉そうに答える術も覚えていった。 そのうちに、道で友人に "Dove vai?"(ドーヴェ・ヴァイ---どこに行くんだい?)と尋ねられれば、間髪を入れずに "Vado a fanculo!"(……ううっ、公序良俗に反する恐れがあって訳せない……)と答えるといった品の悪い冗談も口に出るようになった。 部屋にノックがあったときの返事も習った。 「はーい、ノックがありました。トントン。入ってきてもいいというときは、Avanti(アヴァンティ)と言いましょうねー」 ----ふむふむ、トントンときたらAvantiか。トントン、Avanti、トントン、Avantiだな。 純情な私は、先生にいわれたとおりに頭の中で繰り返したのである。 | |

|
イタリアでは、このように犬でも車を運転する……というのはもちろんウソである。 そーっと近寄って、やっとのことで写したのだ。撮影 : 1981/11 Firenze |
|
そんなある日の朝、安下宿の部屋で私たちが着替えをしていたときのことである。すでに私は着替えを終わっていたが、S氏がまさにズボンを脱いだというその瞬間であった。部屋のドアをトントンとたたく音がするではないか。 私はノックの音に反応して、パブロフの犬のごとくに、元気よく "アヴァンティ" と叫んだのである。 S氏が「あ、まだダメだ」と言ったときには遅かった。バタンとドアが開き、例の美女が顔を出した。一瞬の間があった後、彼女は私の同居人の様子を見て "Scusi" (スクーズィ--ごめんなさい)と言ってまたドアの外に出ていってしまった。 何の用事だったかは忘れたが、彼女が私たちの部屋に来るなどというのは、3か月の下宿中にもその1回だけだったような気がする。 そんなめったにない機会だったのに、S氏はパンツ一丁になった姿を、絶世の美女に見られてしまったのである。 もちろん、S氏の着替えが済んでから、彼女にはもう一度部屋に来てもらった。 「もう、情けないところを見られてしもうたやないか。ダガシくん、こまるよ~」 S氏には、さんざんぶつくさ文句を言われてしまった。 そのたびに「いやあ、ごめんなさい」などと口では言っていた私であったが、本心はそうではなかった。 ----うむうむ、なにはともあれ、日々の繰り返し練習の成果が現れたというもんだ。 と、実は満足感いっぱいの駄菓子青年だったのである。 ところで、S氏とは、日本に帰ってきてから1回会ったきりである。そのあいだに、神戸には震災があった。いまごろどこでどうしているのやら。 Sさん、あのときはゴメンね。これを見ていたら許してくださいね。 | |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページに戻る | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |