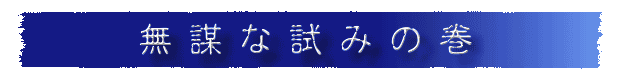 |
|
S氏が私の安下宿に転がり込んできてから1週間ほどたったころのことである。彼は思い詰めたような顔で話しかけてきた。 「ダガシくん、ぼくらはふだん日本語で話しているやろ。でもな、せっかくイタリア語を勉強しにきているんだから、ふだんもイタリア語で話したほうがいいんやないか?」 よっぽど「あんたが来たから、日本語を話す機会が増えたんじゃないか」と言ってやろうかと思ったが、さすがにそれは抑えて一歳年長のS氏をたてることにした。 「じゃあ、そうしてみますかぁ」 S氏の真剣な眼差しを見て、しぶしぶながら同意するしかなかった。 それにしても、初級者2人がへたなイタリア語で会話しているようすを想像しただけで、私の気分は冬の北イタリアの空のように、どんよりと重くなってきたのである。 |
|

|
どんよりとした北イタリアの冬。 モーデナ駅にて。 撮影 : 1981/12 Modena |
|
そもそも同居人のS氏は、基本的にまじめな人だった。冗談は好きだったようだが、その冗談すらもまじめで、めったに笑えなかった。 もっとも、まじめにイタリア語を身につけようという意欲は、尊敬すべき点が多かった。買い物をするときは、必ず店の人と何かしら会話を交わしていたし、会話をするために用もないのに店に入りこみ、いりもしないものを買ってくることもあったほどである。 トラットリーア(安めのレストラン)に入っても、この心がけは忘れていない。近くのテーブルに座っているイタリア人をつかまえて、「あんたが食べてるそれは、何て言うの?」と決まって尋ねるのである。 はじめのうちは、そんなようすを見ていてひやひやしたが、ときにはそれをきっかけにして楽しい会話になるのだから、おもしろいものである。 ある日のこと。注文が終わると、例によってSさんは隣の人にいつ話しかけようかと、スキをうかがっているようすだった。思わず、私は小さな声で彼にささやいたのである。 「Sさん、あれはビステッカ・ディ・フェーガト(レバーのステーキ)でしょう……」 するとSさんは、しょうがないやつだという目つきで私を見て、こう言ったのだった。 「そんなのわかってるわ。わかってるけど、聞いてみるんよ。そうすりゃ、イタリア語の会話の勉強になるだろう……」 その勢いに押されて、私はだまりこんでしまった。 ----ふむう、この人はウソをついてまで勉強しようとしているんだ……。 たいしたことではなかったが、一歳年上のSさんが、ずいぶん大人に感じられた一瞬であった。 |
|
当時は、もちろんこんな立派なレストランには行けなかった。 中部イタリア・アッシージのあなぐら風レストラン。 撮影 : 1990/06 Firenze |

|
|
そもそも、大学を出たばかりの純情で正義感あふれる駄菓子青年は、ウソや曲がったことがそれまで大きらいだったのである。曲がったもので好きなのは、チリソース炒めに入っている芝海老くらいだった。 だが、S氏のこのことばを聞いて以来、気楽にウソがつけるようになり、女性に向かっても歯の浮くようなお世辞が平気で言えるようになった。どんな国に行っても、どんな人と会っても、図々しく振る舞えるようになったのは、S氏の根性に見習うところが大きいと自分では思っている。 ところで、二人がイタリア語で日常会話をするという約束である。 けんめいに努力はしてみた。だが、結局二人とも無口になるだけであった。 「やっぱり、やめようや」 S氏のひと言で、無謀な試みはわずか半日にして中止というハメになったのである。 | |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページ | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |