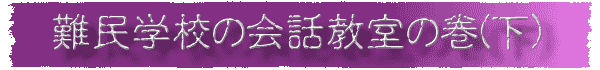 |
フランチェスコの正体もわかったところで、いよいよボランティアの会話教室の初日がやってきた。ちなみに、アラブ人とアフリカ人であふれていたその "学校" は、日本人のあいだで、誰からともなく「難民学校」と呼ばれるようになっていた。 初回の授業当日、私が教室にはいったときには、すでに10数人程度の学生が席についていた。 机は、いかにも会議用といった細長いテーブルを向かいあわせにして、その両側に学生が座っている。そんなテーブルが、細長い教室に4組、計8卓ほど並べられていたであろうか。 細長い教室の奥のほうに、アラブ系と思われる学生が7~8人。手前のほうには、顔なじみの日本人が数人座っていた。 さて、いよいよ授業の開始である。先生は交替制とのことで、初日は40代後半といった感じの上品そうな女性であった。 ひととおり、名前と出身国だけを言うかんたんな自己紹介があった。 教室の入口付近に陣取ったのは、われわれ日本人数人と、まだ10代前半の中国人の女の子1人という東アジア連合である。彼女は、親が繊維関係の仕事をしている関係で、フィレンツェにやってきたとのこと。それにしても、開放政策がとられる前の中国である。国費留学生以外の中国人はかなり珍しかった。 教室の奥のほうに陣取っていたのは、アラブ系の学生が占める西アジア連合であった。出身は、ヨルダン、レバノン、パレスチナといった近東地区が多かったように記憶している。イタリア語のレベルはというと、初級者だった我々とどっこいどっこいで、ちょっぴり安心した。 |

|
私が座っていたのは、東西アジアの国境地帯である。隣のアラブ人学生はなかなか品がよさそうで、あいさつをかわすと、アラビア語で私の名前を書いてくれ、きわめて友好的であった。 ただ、友好的なのはいいのだが、話が止まらないのには困った。全員の自己紹介が終わっても、そのまましゃべりつづけている。私は、ああ、うん、とあいづちを打つのだが、先生のほうが気になって上の空。 こりゃ参ったなと思ったが、それはまだ、来るべき騒乱状態のほんの序の口にすぎなかったのである。 |
|
| 当時、冬のフィレンツェは観光客の姿も少なく、ふだん着の町の姿を見ることができた。 ドゥオーモの横にて 撮影 : 1981/12 Firenze |
||
|
その日のイタリア語会話は、日常のあいさつというごく初歩のところからはじまった。そんなレベルの話でも、隣のやつに気をとられている私を除いて、東アジアの人びとは、きちんと先生のほうを向いて耳を傾けている。 ところがである。西アジア軍団は、一人残らず私語を続けているではないか。 私の隣の学生は、まだひそひそ声でしゃべっているからいいようなものの、奥のほうのやつらは、ほとんど地声で話しているのだ。 大きな教室ならまだしも、10数人しかいない小さな部屋である。さすがに先生も「静かに」というのだが、話がやむのはその後、数秒間だけ。日本人と中国人は、たがいに顔を合わせて、あきれるほかなかった。 そんな状態がつづき、私たちのいらいらが爆発しそうになったとき、ついに日本人の一人、イッセイくんが爆発してしまった。彼については、後にちょっとした事件が起きるので、そこで詳しく紹介することになるだろうが、千葉県出身で私よりも5歳ほど年下の男である。 「Sta’zitto(黙れ)!」 あたりに響く大声に、教室は一瞬静まりかえった。 ----おお、よくぞ言った、イッセイくん……でも、なんかマズいふんいきかもね……。 先生も、ややとまどっているようすである。気の小さい駄菓子青年は、この教室の行く末を心配した。 ----これがもとで、アジアの東西対立が勃発して、血で血を洗うけんかにならなければよいが……そんなことになったら、戦争慣れしている彼らには勝てそうもないしなあ……。 しかし、それは杞憂であった。その数秒後には、何事もなかったかのように、彼らはまた私語をはじめたのである。 |
|
| 夕暮れどきのフィレンツェ中心部。 遠くから豆腐屋のラッパの音が……するわけないか。 撮影 : 1981/09 Firenze |

|
|
----ダメだ、こりゃ。 日本人と中国人は、そのあまりの状況に、ただただ無力感を抱くだけであった。 と、そのときである。先生がにこにこしながら、奥のほうにいる一番うるさいやつを立たせた。 「あなた、なんていう名前だっけ」 「ガブラルです」 素直に立ち上がって彼は答えた。でかい図体だが、なかなか愛嬌があってかわいらしい目をしている。急に指名されてびっくりしたのか、おどおどしているようにも見えた。 「じゃあ、ガブラル君。あいさつからはじめましょうね……ブォン・ジョルノ!」 ガブラルは、まるでトイレを我慢している小学生のようにおどおどしていたが、ややあって、ようやく思い切ったように答えた。 「ベンジョルノ!」 このことばが耳にはいるやいなや、私は気管支の奥のほうから、笑いがこみあげてきた。しかし、それが外に出てくるのを必死にこらえたのである。もちろん、へたに大笑いをして、こんどこそ国際問題になっては困ると考えたからだ。 で、苦しみつつも、ほかの日本人のようすをうかがってみたところ、やはり一人残らず体を震わて、けんめいに笑いをこらえているではないか。そんなようすを、そばにいるアラブ人と中国人がけげんそうな顔で見つめている。 その後まもなく安下宿の朋友となるS氏は、親切にも隣席のアラブ人に向かって説明をしていた。 「ベンジョは日本語でガビネットだから、ベンジョルノはガビネットジョルノなんだ」 はたして、これで私たちが笑っているわけを理解してくれただろうか。いずれにしても、私はしばしのあいだ、のどをひくつかせて、笑いを押し殺すしかなかったのであった。 まあ、そんな騒乱のなかで、難民学校の第1日目の授業は終わったのである。 翌日学校に行ってみて驚いた。なんと、我々のクラスが、東アジア組と西アジア組に分割されたというではないか。あまりにも突然の措置であった。 おかげで、2日目からは平穏な会話教室が続くことになったのだが、はたして西アジア組の授業がどのように続いていったのかは、いまでは知るすべもないのである。 そうそう、それから数日の間、日本人どうしのあいさつが「ベンジョルノ」になったのは言うまでもない。 |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページ | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |