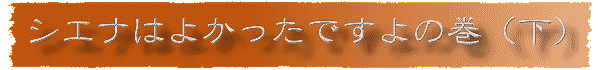 |
さて当日の朝、われわれ男3人と女2人は、フィレンツェ駅裏にあるバスターミナルに集合した。なんとなく、小学校時代の遠足の気分である。 T島氏の手には、朝日選書の「イタリア 美術・人・風土」三輪福松著があった。いま思うと信じられないのだが、当時イタリアに関する文化的な書籍で、すぐに入手できる本といえば、これくらいだったのだ。 この本をT島氏はいつも手元に置き、ことあるごとにページを繰りながら、「シエナの中心にあるカンポ広場は貝を型どったもので、面の数はシエナ市内の町の数を表しているんですよ」とか「シエナはフィレンツェのライバルでしてね……」といったことを、聞かれもしないのに周囲の日本人に説明していたのである。 いまでこそ、シエナといえば世界遺産にも指定され、ガイドブックに大きく扱われている町である。しかし、当時はといえば、山と渓谷社のガイドブックでフィレンツェの近郊都市という扱いで3分の1ページが割り当てられている程度。ほかはといえば、「朝日旅の百科」でカンポ広場が写真で紹介されているくらいであった。 |
|
実は、その1か月ほど前に私は一人でシエナに出かけていた。だが、例によってうろうろ歩きまわるのみの旅。地元に長くいた人がいれば、また違う楽しみもあることだろう----そんなことを考えながら、バスに乗り込んだのであった。 フィレンツェからシエナに向かう道は、トスカーナの丘をつっきって走る。両側になだらかな起伏のぶどう畑を見ながら、特急バスはつねに時速100キロ前後で快走していった。 |

| |
| シエナの町は、どこをとっても絵になる。これはドゥオーモの裏。 撮影 : 1981/10 Siena |
||
|
途中のサン・ジミニャーノでのんびりしてしまったり、乗換えで手間取ったりしたものの、なんとか2時前後にはシエナに着くことができた。 「……」 T島氏の口からはほとんどことばが発せられなかったが、そのゆるんだ頬と半開きになった口を見れば、彼がいかほど満足しているかは容易にうかがうことができた。 「これがマンジャの塔ですよ。1年に1回くらい、てっべんから落ちる人がいるそうですけど……」 「わあ、懐かしいなあ、この道を通っていつも学校に通っていたんですよ」 感動がだんだんとことばになっていったのだろう。歩が進むにつれ、T島氏は雄弁になっていった。 バスターミナルから中心部へと行く道は、上ったり下ったりしながらだらだらと続いていく。でも、道の両側に並ぶ店を見るだけでも楽しい。シベリア鉄道で会った女性2人もご機嫌の様子であった。 そして、カンポ広場でぼんやりしたり、ドゥオーモの博物館を見たりしているうちに、あっというまに日は傾いてしまった。 「じゃあ、そろそろ食事にしますか」 T島氏の提案で、彼のなじみらしいカンポ広場近くのトラットリーアに入ることにした。 「ここのパスタは最高ですよ。さあさあ、好きなものを注文しましょう……おお、おお、ブォーナ・セーラ!」 久しぶりに顔見知りの店員に会ったのだろう。T島氏は満面に笑みを浮かべ、大げさな身振りで店員と握手を交わしていた。広い店内には、20人ほどの客がいただろうか。ざわざわした雰囲気は、いかにも町の定食屋にふさわしかった。 「じゃあ、ボクはスパゲッティ・アッラ・アッラッビアータね」 一皿目の料理として、そのころ病みつきになっていた唐がらしニンニク入りトマトソース味のスパゲティを注文した駄菓子青年である。ほかの人も思い思いに好きな料理を注文したのであった。 やがて、待ちかねた私たちの前に、パスタが運ばれてきた。 店長らしき太ったおじさんは、にこにこしながら私の前にやってきた。 「ほら、唐がらしとナイフを持ってきたから、好きなだけ切って交ぜるといい。ただ、カットしたあとでその手を目に入れちゃいけないぞ。目の玉がヒリヒリして死にそうになるからな。ワッハッハ」 T島氏はT島氏で、「ここのパスタはおいしいんですよ」と何度も何度も繰り返す。こうして、私たちは和やかな雰囲気のなかで、次々に目の前のパスタを口に運んでいったのである。 |
|

|
夕暮れのカンポ広場。 撮影 : 1981/10 Siena |
|
ところがである。いまひとつ味がぱっとしないのだ。けっしてマズいというわけではないが、あえて言えばキレがない。同じ安食堂とはいえ、フィレンツェのそれにくらべると、寝ぼけたような味であった。 とはいえ、T島氏のお勧めの店である。私の体調が悪いだけかと思い、周囲の人の様子をうかがってみた。すると、やはり浮かない顔をしたS氏と目があった。いつもの通りの細い目であったが、その目は「イマイチやな、ダガシくん」と語っていた。 T島氏はと見ると、それまでゆるみっぱなしだった彼の顔に、微妙な変化が生じていた。口数も少なくなっていったのは、ただ食べるのに忙しかったからだけではないだろう。もっとも、そのあまりにも微妙な変化は、何週間も付き合っていた私とS氏だからこそ気がついたに違いない。女性陣2人は、そんなことともつゆ知らず、相変わらず元気ではしゃいでいたのであった。 その後は、何をどう注文したのか覚えていない。私もS氏も「ウマい、ウマい」と口では言っていたが、本心からではなかった。T島氏も笑顔を浮かべて「そうですか」と言うのだが、なにか落ち着かない様子である。いつもの傲慢なまでの元気さが消え、申し訳なさそうな表情を浮かべるのだ。 こうして、表向きにはにぎわしく、実はその底に戸惑いをはらみつつ、食事は進んでいったのだった。 勘定を払って店を出ると、もうあたりは真っ暗であった。帰りのバスでは、みんな疲れが出たのか、ぐっすりと寝入ってしまった。そんななか、寝付きの悪い私は、さきほどの出来事を振り返っていたのである。 ----確かに、去年までのT島さんだったら、ウマいと感じていたんだろうなあ。でも、いまや花の都のフィレンツェ暮らし。知らず知らずのうちに舌が肥えてきたんだろう。いいことなのやら、悪いことなのやら……。 こうして、シエナへの日帰り旅行は幕を閉じたのであった。 以後、T島さんの口から「シエナはよかったですよ」ということばを聞くことはなくなった。 |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページ | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |