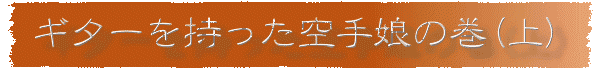 |
今回の話は、安下宿のならびにある、これまた安トラットリーアからはじまる。 夜の8時ころだっただろうか。私とS氏とT島の3人は、知り合ったばかりの男性2人と夕食をとっていた。一人はアカデミア美術学校にかよう日本人。年齢は、私より3、4歳上だっただろうか。例によって、町なかを歩いている彼を、S氏が“スカウト”してきたのである。もう一人は、その彼と同居してるギリシャ人。やはりアカデミア美術学校に通う大柄な彼は、純情で気のいいやつだった。 そんな野郎5人が、地元の安い赤ワインをがぶがぶと飲みながら、とりとめのないことを話し合っていたと想像していただきたい。 一通り食事も終わったころだったろうか、どうも隣に座っているS氏の様子がおかしい。会話には加わっているのだが、何か落ち着かないである。 トイレにでも行きたいのかと思っていると、いきなり隣のテーブルに向かってイタリア語で話しかけた。2、3メートル離れたそのテーブルには、私たちとほぼ同年代と思われるイタリア人のカップルが座っていたのである。 私は、いやな予感がした。 ----この人は、また「あなたの食べているのは何ですか」って声をかけて、イタリア語の会話練習をはじめるんじゃないだろうなあ。相手がヒマなおじさんならまだしも、今回は若いカップルだぞ……。 小心者の私は、これから起きるかもしれない出来事をいろいろと頭に思い描きながら、S氏の言動を視野の端で監視していた。 ----まあ、ここは他人のふりをすることにしよう。変な東洋人ということでひとくくりにされちゃたまらないしなあ……。 もっとも、誰がどう見ても他人のはずがない。 ほかの人たちはというと、みないいかげんワインがまわっているので、S氏の不審な行動などはまったく気にかけていない様子であった。私はそんな彼らと会話を続けながらも、横目でS氏の様子をうかがうことは怠らなかった。 | |

|
以前は、ライトアップなどといったことはやっておらず、ミケランジェロ広場にもいまほど人はいなかった。 撮影 : 1985/11 Firenze |
|
そんな、聖徳太子なみの集中力を数十秒ほど続けていたころであろうか、イタリア人の女性とS氏とが、ほぼ同時に驚いたような声を上げたのである。 「どうしたんですか」 すると、S氏はただでさえ細い目をさらに細めてこう言った。 「いやな、共通の知り合いがいたんよ」 「知り合い?」 「さっきからな、カラテとかMさんとかいう名前が聞こえていたから、聞いてみたんや。そしたら、ミラノに住んでいる知り合いでカラテの先生をやっているMさんのことだった」 そこでもう一度、相手のテーブルを見た。女性はいかにも格闘技向きといった感じのがっしりとしたタイプである。男のほうはほっそりしておとなしそうなやつであった。 こちらはかなりワインが入っているし、年代が近そうなこともあって、あいさつもそこそこに、あれこれとしゃべりはじめた。 イタリアに何ヵ月もいながら、妙齢のイタリア女性とゆっくり会話などする機会がなかなかない我々である。しかも、相手は空手を通じて日本にも興味を持っている。いきおい、イタリア語会話にも熱が入った。 |
||
|
2人は北イタリアのトリーノから来たという。その後の話題は、日本とイタリアの文化の比較から日本語の話まで、実にインテリどうしの会話にふさわしく、教養あふれるものであった……ような覚えがあるが定かではない。 ちなみに、私たちは代わる代わる自分の言いたいことを、ここぞとばかりに話すのだが、相手はもっぱら女性のほうが受け答えをしていた。あんまり熱心に話しては、男のほうが焼き餅を焼くのではないかと、ちょっぴり心配であった。 |

| |
| 安下宿も安トラットリーアも、こんな昼なお暗い路地にあった。 撮影 : 1981/10 Firenze |
||
|
でも、かえって下心なしで、気楽に話せたのはよかったような気がする。男のほうはといえば、落ち着いた様子でにこにこしながら話を聞いていた。 会話は、のどかにたんたんと続いていった。でも、そんななかで、ただ一瞬だけ場に緊張が走ったことを白状しなければならない。それは、彼女が次のことばを発したときである。 「ミ・ピアーチェ・ダガシ」(私はダガシが気に入ったわ) 「いやあ、あのときは驚いたわ。ダガシくん、やるじゃないか。ミ・ピアーチェなんて、かなり気に入っている証拠やで」 店を出たところでS氏は声をひそめて私にいった。もっとも、大きな声でいったとしても、そばにいたイタリア人カップルにはわからなかっただろうが。 「やるじゃないかって言ったって、れっきとした彼氏がとなりにいるじゃないですか。まあ、なんなんだか……」 そうは言ったものの、まんざらでもない気分ではあった。 店を出たのは十時をまわっていたかもしれない。外にはほとんど人通りがなく、郊外に住んでいる美学生2人はすでに帰途につき、残りの私たち日本人3人とイタリア人カップル2人が、夜更けのフィレンツェ中心部をうろついた。 「実は、私たちフィレンツェは初めてなのよ。教えてくれる」 「おお、じゃあ、案内しますよ。ドゥオーモまで行きましょう」 「ほら、ここ」 当時は、ライトアップなどという不粋なことをしていなかったが、街路灯の緑色っぽい光を浴びて、ドゥオーモはいっそう存在感をましていた。 「おお、すばらしい!」 彼らは目の前の大理石の教会を見上げながら、なぜか小さな声で感動のことばを発した。 「いやあ、ダガシくん、フィレンツェで日本人がイタリア人を案内するなんて、おかしなもんやなあ」 S氏はしきりに不思議がっていたが、私はそれほど不自然に感じなかった。その代わり「こんなこともアリなんだなあ」と、ちょっとうれしかった。 「外国人にイタリアを案内されて、変やないのかな」 「いやいや、Sさん、これでいいんですよ」 よく考えれば、つい百年前まで、彼らの住んでいるトリーノとこのフィレンツェは別の国だった。彼らにとって、ここは外国に来たような気分なのかもしれない。 ----いや、待てよ。イタリア人にとってのイタリアという国は、日本人にとっての日本とは違うのかもしれない……。そうか、中国人にとっての中国や、ロシア人にとってのロシアは、もしかしたら日本人にとっての日本とまったく違うのかも……。これまで、そんなことは考えたことがなかったなあ……。 なかなかいいところまでたどりついた駄菓子青年であった。もしかすると、あと一歩、思索を深めれば、少しはマシな世界観が確立していたかもしれない。でも、それにはアルコールが回りすぎていた。 ----そうかぁ。じゃあ、こんど京都か北海道にでも行ったときには、現地に住む外国人に道案内をしてもらうのもいいかもね。 そこまで考えついただけで上出来ということにしよう。 町の中心部を歩きまわったのは30分ほどだろうか。彼らは、フィアットの小さな車に乗ってトリーノに帰っていった。 別れぎわに、私たちはお互いの住所を交換した。彼女は「手紙ちょうだいね」と何度も繰り返していた。そのことばが、その後の日本とイタリアの友好に大きな影響を与えることになろうとは、私の隣でへらへら笑いながら手を振っていたS氏には、想像もつかなかったに違いない。 (つづく) |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページ | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |